【セミナーレポート】2024/08/30 地域包括ケアシステム推進のための実践ガイド
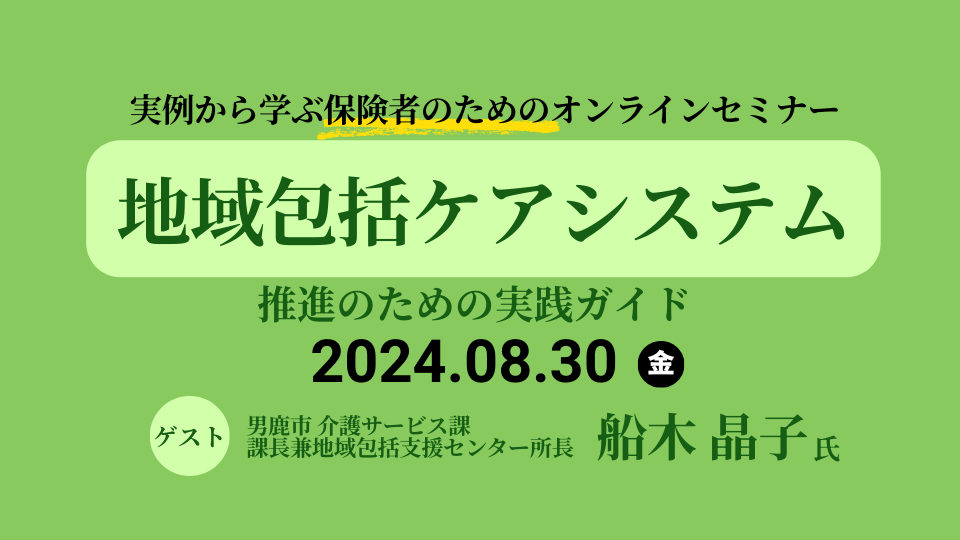
| 開催日時 |
2024年08月30日 13:30〜15:00(接続開始13:15)
|
|---|
セミナーレポート
第1部 13:30~14:20 地域包括ケアシステム概論
講師:株式会社日本経営 顧問 松川竜也
第2部 14:20~14:45 事例紹介~男鹿市様とのトークセッション~
ゲスト: 男鹿市 介護サービス課 課長兼地域包括支援センター所長 船木 晶子氏
インタビュアー: 株式会社日本経営 主任 宇野 明人
第3部 14:45~15:00 地域分析における指標と仮説立て
講師:株式会社日本経営 課長代理 近藤瑛佑
はじめに 深刻化する介護保険制度の課題
本セミナーは、日本の介護保険制度が直面する課題をデータから読み解き、地域包括ケアシステム推進における「概論と実践事例」を学ぶことを目的としています。多くの保険者や行政担当者から「他の成功事例が自地域の答えにならない」という悩みが寄せられており、知識の習得だけでなく、参加者の実践を後押しすることに焦点を当てました。
第1部 地域包括ケアシステム概論(介護保険を取り巻く現状と課題)
松川氏(主任介護支援専門員)は、まず日本の介護保険を取り巻く厳しい現状を解説しました。特に、2040年頃にピークを迎えると予測される65歳以上の高齢者数や、2035年頃まで一貫して増加する85歳以上の人口に言及。また、要介護認定率は年齢が上がるほど上昇し、85歳以上では60.6%に達します。一人当たりの介護給付費も85歳以上で急増していることがデータから示されました。さらに、認知症高齢者が2025年には約700万人に増加すると推計されること、そして世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく現状が示されました。これらの世帯はより多くのサービスを必要とすることがデータで分かっています。
第2部 男鹿市とのトークセッション
男鹿市介護サービス課 課長の船木氏とのトークセッションでは、「なぜこの施策が必要なのか」という根拠を示し、関係者の合意を得て進めることの重要性が語られました。男鹿市では、ショートステイの長期利用増加という課題に対し、データに基づいた分析と関係者の合意形成を重視し、行政が費用抑制のために言っていると思われがちな部分を、第三者であるコンサルタントがデータに基づき、専門的な見知から根拠を説明してくれることが事業を円滑に進めるうえで重要な役割を担っていたと語ってくださいました。この取り組みの結果、関係者の間で「地域包括ケアシステムは建前」という空気がなくなり、意識の変化が見られ始めました。現在は、警察、消防、民生委員なども含めた多職種連携を強化し、地域全体を巻き込んだ具体的な取り組みが進められています。
第3部 地域分析における指標と仮説立て(成果を出すための分析手法)
近藤氏からは、データ活用の重要性について解説がありました。統計的なデータ(マクロ)と個別支援の経験(ミクロ)を掛け合わせることで、地域が抱える課題の本質を見抜くことができると説明がありました。
成功事例として、西伊豆町の取り組みが紹介されました。この町の介護認定の申請理由の1位が「転倒・骨折」であることをデータにより特定し、リハビリ専門職が不足している状況下で、住民が主体となって「シルバーリハビリ体操」を普及させたところ、転倒・骨折が認定理由のトップ3からなくなり、介護認定率が下がりました。そして結果として、第9期介護保険料が第7期から1,700円も下がったという成果に繋がりました。
まとめ 持続可能な地域づくりのために
セミナー全体を通じて、持続可能な地域包括ケアシステムを推進するためには、「データに基づいた客観的な分析」「多職種・住民の巻き込み」「ビジョン達成型の計画」の3点が重要であることが示されました。
特に、男鹿市介護サービス課 課長の船木氏とのトークセッションでは、地域の課題を共有し、解決策の必要性を理解することから始める、というプロセスを具体的に示し、同じ悩みを持つ自治体のみなさまに参考となる非常に良い実践例であり、参加者である都道府県および市区町村の地域包括ケアシステム推進担当者、保険者のみなさまにとって自地域での実践に向けたヒントを得られる有意義なセミナーとなりました。
みなさまの組織が抱える介護保険事業の課題解決に向け、より深くデータ分析をしたい、または具体的な施策立案について相談したいとお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
医療・介護政策に精通し、調整力に長けたコンサルタントが行政・自治体の政策実現に貢献します
私たちコンサルタント活用の選択肢もぜひ、ご検討ください


