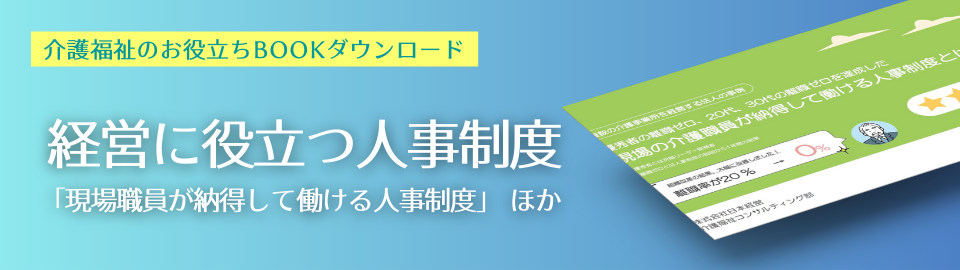最低賃金の上昇にどう備える?介護福祉事業所が直面する課題と改革のポイント

-
業種
介護福祉施設
- 種別 レポート
介護福祉業界において、最低賃金の上昇は経営者にとって避けられない課題となっています。政府は全国平均1,500円 を目標に掲げ、実際にここ数年は毎年50円前後の引き上げが続いています。物価高騰や人材不足の進行も背景にあり、この傾向は今後も止まることはありません経営者には「その場しのぎ」ではなく、将来を見据えて制度を見直すことが求められています。
▶関連するお役立ちBookはこちら
最低賃金上昇の背景と今後の見通し
最低賃金が上がり続ける背景には、いくつかの政策的要因があります。
第一に、政府の掲げる「全国平均1,500円」の実現です。これは単に労働者の生活水準を高めるためだけでなく、地域間の賃金格差を縮小し、人材流出を防ぐ狙い もあります。東京や大阪のような都市部と地方の賃金差が広がる中で、全国的な底上げは国の重要課題となっています。
第二に、物価高騰の影響です。エネルギー価格や食料品価格の上昇は労働者の生活を直撃しており、賃金が追いつかなければ生活が成り立ちません。そのため最低賃金の引き上げは社会的要請ともいえます。
では、今後の水準はどの程度を想定すべきでしょうか。仮に毎年6%ずつ上昇するとすれば、2025年に1,118円の地域は2027年に1,256円、2030年には1,495円となります。全国平均1,500円という政府目標を見据えると、特に都市部では早期に到達し、地方も追随していくでしょう。
この動きを「まだ先のこと」と軽視するのは危険です。最低賃金が上がれば、採用市場における時給や初任給も連動して高騰します。その結果、 新規採用コストが膨らみ、さらに定着率の低さが加われば、法人の人件費比率は年々上昇していきます。介護報酬の伸びが限定的である以上、経営構造の見直しは避けられません。最低賃金への 対応は「来年どうするか」ではなく、「数年後の組織をどう描くか」を考える契機なのです。
内部環境に潜む課題
最低賃金に合わせて給与を引き上げるだけでは、内部に深刻な歪みを生じます。その代表例が「給与の逆転現象」です。新人と中堅職員の給与が同じ水準、あるいは逆転する状況は、職員の不満を引き起こします。
また、毎年の改定を継ぎ足しで対応していると、「なぜこの金額になったのか」を合理的に説明できなくなります。制度がブラックボックス化し、職員の納得感は大きく損なわれます。その結果、「頑張っても報われない」という感情が広がり、離職や採用難につながる悪循環が生じるのです。
よくある誤った対応とその弊害
最低賃金の確認方法は、時給・日給・月給といった給与計算の算出方法によって異なりますが、いずれ最低賃金対応でついやってしまいがちな誤りを、具体例とともに 整理してみましょう。
最低賃金を下回る職員だけ給与を引き上げるケース
ある介護福祉事業所では、毎年の最低賃金の引き上げに合わせて、基準を下回る職員の給与だけを修正していました。一見すると合理的に思えますが、結果として3年間勤めてきた職員と新規採用の新人の給与がほぼ同額になってしまったのです。そのため、 中堅職員からは「努力や経験が評価されていない」という声が噴出し、モチベーションの低下と離職の加速を招きました。採用コストは増加し、組織の安定性は大きく損なわれました。
調整手当で一時的に補填するケース
別の事業所では、最低賃金の上昇に対応するため「特別調整手当」を設け、給与に上乗せする形を取りました。しかし、調整手当は本給と異なり、合理的な算定根拠が乏しいまま支給されるため、数年経つと「なぜ自分には付与されないのか」「なぜ隣の職員と金額が違うのか」といった不満が広がりました。制度が複雑化し、説明困難な状態に陥った結果、組織内の信頼関係を損なう事態となったのです。
このように、短期的には対応できても、長期的には制度の信頼性を揺るがすことになります。最低賃金への対応は「その場しのぎ」ではなく、組織の基盤を整える取り組みとして進める必要があります。
正しい対応のステップ
最低賃金の対応を持続的に行うには、段階的なプロセスを定着させることが不可欠です。
まず、基準を下回る職員の人数と必要な引き上げ額を正確に算出します。
次に、その調整が職種間・等級間の給与差に与える影響を確認し、逆転や不公平が生じていないかを検証します。
そして最後に、毎回の対応を属人的に行うのではなく、一定のルールに基づいて処遇を決定できる仕組みを整えます。
これにより、法令遵守と職員の納得感を両立させることができ、組織としての一貫性を維持することが可能となります。
公平性と納得感を軸とした制度設計
最低賃金の対応を超えた根本的な課題は「職員が納得できる制度かどうか」です。ここで重要になるのが「公平性」です。
平等 は、すべての職員を同じように扱うことを意味しますが、それでは努力しても報われないという不満が残ります。一方で公平 は、貢献度や成果に応じた処遇を与えることです。例えば同じ年数勤務していても、貢献度 や成果が異なれば、その差を適切に処遇へ反映させる必要があります 。この違いを理解し、制度に組み込むことが、納得感を高める鍵となります。
制度設計においては、人事制度の三本柱 等級制度 人事考課制度 賃金制度 これらが連動する必要があります。法人が期待する役割を明確にし、その遂行度を評価し、評価結果を処遇に反映させる。この連動が欠けると、制度は形骸化し、職員の信頼を失います。
法人特性に応じた制度改革
制度改革は、他法人の成功事例をそのまま真似ても機能しません。大規模法人と中小法人では職員数も原資も異なり、都市部と地方では採用市場の状況も大きく違います。したがって、まずは自法人の課題を正確に把握することが出発点となります。
給与水準、職員構成、地域の採用環境を分析し、どこに歪みがあるのかを可視化する。
その上で、自法人に合わせた制度設計を行うことが必要です。
自力で対応することも可能ですが、情報が氾濫する中で本質的な課題を見抜くのは容易ではありません。ここにこそ、専門的な知見を取り入れる価値があります。経験豊富な専門家の支援を受けることで、持続的で実効性のある制度改革を進めやすくなります。
まとめ
最低賃金の上昇は、介護福祉業界にとって避けられない現実です。しかし、それを単なるコスト増と捉えるか、人材確保と制度改革の好機と捉えるかで、法人の未来は大きく変わります。
給与調整にとどまらず、公平性と納得感を重視した人事制度を再構築することが、人材流出を防ぎ、持続的な成長につながります。そのためには、自法人の課題を正しく把握し、長期的な視点で制度を整えることが不可欠です。そして、その過程において専門的な知見を取り入れることは、経営者にとって有効な選択肢となるでしょう。
▶関連するお役立ちBookはこちら
本稿の監修
浦越 恵嗣
株式会社日本経営 介護福祉コンサルティング部
尾花 龍
株式会社日本経営 介護福祉コンサルティング部
株式会社日本経営
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。