白熱の人事評価判定会議 /日本経営のケイエイ
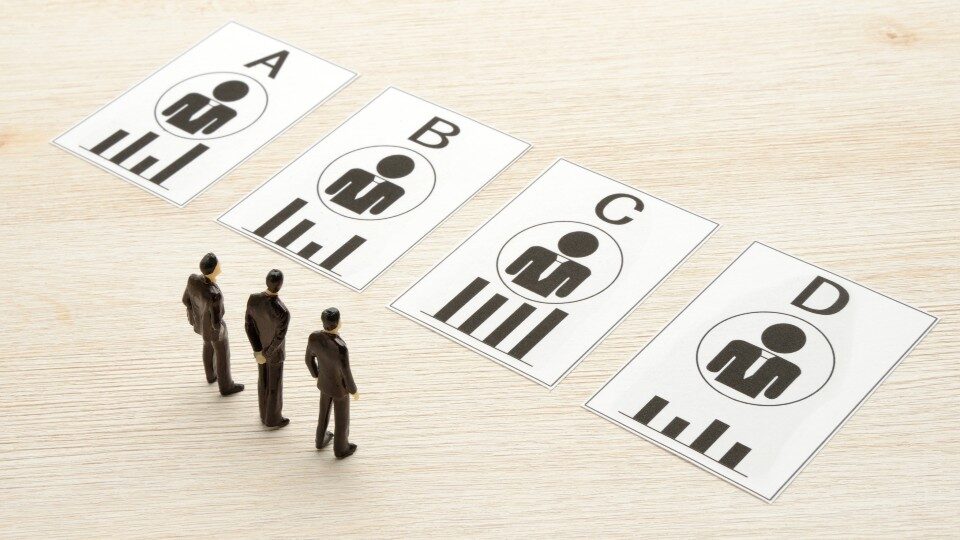
-
業種
企業経営
- 種別 レポート
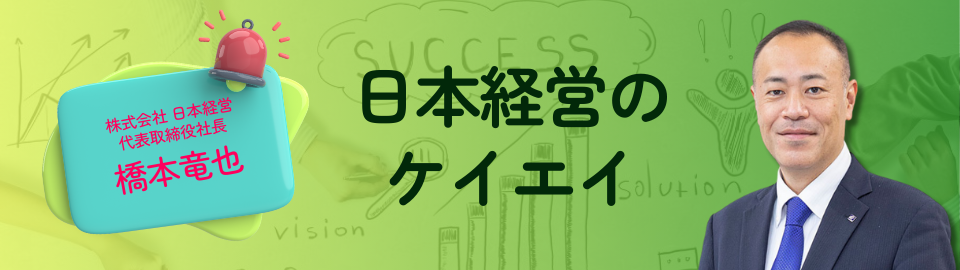
(株)日本経営での取り組みや私が考えていることなどを発信しています。
皆様の経営のヒントや新たなアイデアなどにつながれば幸いです。
白熱の人事評価判定会議
株式会社 日本経営 / 代表取締役社長 橋本竜也
(株)日本経営の人事評価の構成
当社の人事評価は、「行動評価」と「目標達成度評価」をそれぞれ年1回実施しています。
当社の事業年度は10月~9月となっており、定期昇給と昇格も10月に実施しています。人事評価の実施時期とその結果の反映も、このスケジュールに合わせて実施しています。
行動評価は5月に実施し、7月の賞与と10月の昇給に反映させます。目標達成度評価は10月に実施し、12月の賞与に反映させます。つまり、12月の賞与は100%前年度の成績で決定しており、そのため金額や評価による差も大きくなっています。
行動評価の決定が重要
目標達成度評価は目標に対してどうだったかを判定するだけなので、目標が適切に設定されていればほとんど議論の余地がなく、スムーズに評価結果を決定できます。
難しいのは、定性的な基準に基づいて判断する行動評価です。難しいですが、行動評価はとても重要です。なぜなら、本人が求められる役割を果たしているか、実力が身についているかということを判定するものだからです。もし、行動評価をおろそかにして、目標達成度評価だけを重視すれば、結果至上主義の会社に陥り、それは組織の殺伐さを招いたり、場合によっては崩壊の要因となってしまいます。
業績はその時々の状況によって変動することもありますが、人材育成、組織づくりの観点から考えれば、行動評価をしっかりと行い、本人にフィードバックすることが極めて重要です。
ところが、この行動評価は簡単なものではありません。従業員が役割を果たしているか、パフォーマンスを発揮しているかを見極めていくわけですから、難しいのは当然です。そのため、適切なプロセスを踏んで取り組むことが重要です。
行動評価を適切に行うための重要な2つのルール
まず、ルールに従って評価者が評価をすることが大前提です。そのルールは非常にシンプル。
①クリア基準
低い評価段階から順に確認していき、そこをクリアしていたら次の基準を確認する。例えば、CをクリアしていたらBを確認、BをクリアしていたらAを確認ということ。CがクリアできていないのにBやAはあり得ない。
②常態基準
普段のレベルを判定する。たまにできた、たった1,2回失敗があった ということは判定の根拠にしない。
この2つのルールを評価者が徹底的に理解し、そのうえで評価を実施することが重要です。この共通認識をもとに判定会議も行います。当社の判定会議では、他部門から「それはクリア基準になっていないのではないか?」とか、「その行動はたまたまで、普段はできていないのではないか?」といった指摘が入ることもあります。
白熱の判定会議
当社では一般的な企業と同様に、一次評価と二次評価を順に行っています。直属の上司が評価し、その後に部門長、さらに担当役員が評価します。担当役員までの評価結果をもとに、全部門長と全役員が集まって、最終判定会議を開きます。当社には 250人ほどの社員がいますが、3,4時間かけて集中的に行っています。
当社の人事評価の総合判定結果は、S、A、B+、B、B-、C、Dの7段階です。最終判定会議で全従業員について議論するのは現実的ではありません。そのため、最終判定までの間に部門長と担当役員がしっかりと意見交換を行っているため、B+ , B , B- の評価については確認をするだけで深い議論はしません。重点的に議論するのは、S , A , C , D の評価となった従業員についてです。
SやA評価になる従業員は、当社を代表する社員といっても過言ではないので、本当にその評価にふさわしいのかという視点で議論しています。S , A 評価になっている従業員については部門長から理由を説明してもらいますが、参加者から多くの質問や意見が出ることもあります。その場合は、その対象者の評価表を開いて全員で評価項目を一つひとつ確認することもあります。
たとえば次のようなやりとりがなされます。
「他部門との連携で成果を上げていると判定されているが、当部門から見るとこの従業員は非協力的に見えるがどうか?」
「周囲から認められる専門性が複数身についているという評価になっているが、具体的にはどのような専門性で、それは業績につながっているのか?」
決して他部門の従業員を批判したいとか、評価を下げたいということではなく、前向きな意見交換を行っています。そして、最終的にSやA評価になった従業員は、所属部門の成績優秀者というよりも、(株)日本経営の成績優秀者だという認識を全員が持つようにしています。役員や部門長がこの共通認識を持つことでそうした従業員をフォローしたり、プロジェクトに声を掛けたりすることができます。
CやD評価となっている従業員については、本当にその評価でよいのか、十分に育成や支援をした結果、それでも役割を果たせていないのか、職務適性があっているのかといったことを議論します。ここでもさまざまな意見が出ます。
たとえば、
「当部門との連携プロジェクトでは、リーダーシップを発揮してくれているが、この項目はもっと高く評価してもよいのではないか?」
「ムードメーカーとしていい役割を果たしてくれていると感じているが、人事評価としてはその部分の評価は該当するものがないか?」
「あの案件は難しい案件だと聞いたが、彼の貢献が大きかったのではないか?」
こうした議論を重ね、やはりもっと詳しく見たほうがよいとなれば評価表の中身を見直し、評価項目一つひとつを詳しく確認して、最終結果を決定します。
人事評価判定会議は人的資本経営に欠かせない
このようにしっかりと人事評価判定会議を実施することで、人事評価が単なる給与・賞与・昇格決定のツールではなく、人的資本経営の重要な機能として活かされます。
① 直属上司の主観ではなく会社として評価を確定できる。
② 確信をもって本人に結果を伝えることができる。
③ 育成の視点で本人にフィードバックができる。
④ 役員・幹部が成績優秀者やサポートが必要な人材を共通認識できる。
⑤ 人材育成の文化を役員・幹部から醸成できる。
適切に判定会議を行うことで、こうした効果があるでしょう。人数が非常に多ければ、会社全体ではなく分割する必要はあるでしょうが、それでも人事評価の判定会議、特に行動評価の判定会議は力を入れて取り組んでいただきたいと思います。それだけの価値があるものだと確信しています。
人事評価の実施にもはやシステムは欠かせない
当社では一次評価から三次評価、最終判定会議までを1か月弱で行っています。さらに、一人ひとりに踏み込んだ判定会議も行っています。このような人事評価を運用するためには、何らかの人事評価システムがなければ不可能です。
もしシステムを使っていなければ、
- 結果の一覧を作成するだけで膨大な作業が発生します。
- 判定会議で一人ひとりの結果を確認するためにはエクセルや紙を引っ張ってこなければなりません。
- 判定会議の場で評価結果の修正をしたくても すぐにはできません。
当社では、これらの課題を解決するために、自社製品である「人事評価Navigator」を使って人事評価の実施と判定会議を効率的に行っています。皆様も人事評価を効果的に実施するためにも人事評価システムをご活用されることをお勧めします。
※これまでの記事は、こちらからご確認いただけます
このレポートの執筆者

橋本竜也
株式会社 日本経営 代表取締役社長
組織人事コンサルタント
1999年入社以来、人事コンサルティング部門にて、クライアントの人事制度改革に携わるほか、不採算企業の経営再建にも従事。コンサルティング実績は上場企業から中堅・中小企業まで150社を超える。「良い経営は人を幸せにする、悪い経営は人を不幸にする」を基本スタンスに、人事コンサルティングや経営顧問を行っている。
<著書>
「チームパフォーマンスの科学」幻冬舎2021年12月
「中小企業の未来戦略を具現化する!組織マネジメント実践論」プレジデント社2022年10月
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
企業向けセミナー・サービスのご紹介





