病院におけるコスト適正化の方法とは?|調達支援サービスの導入事例
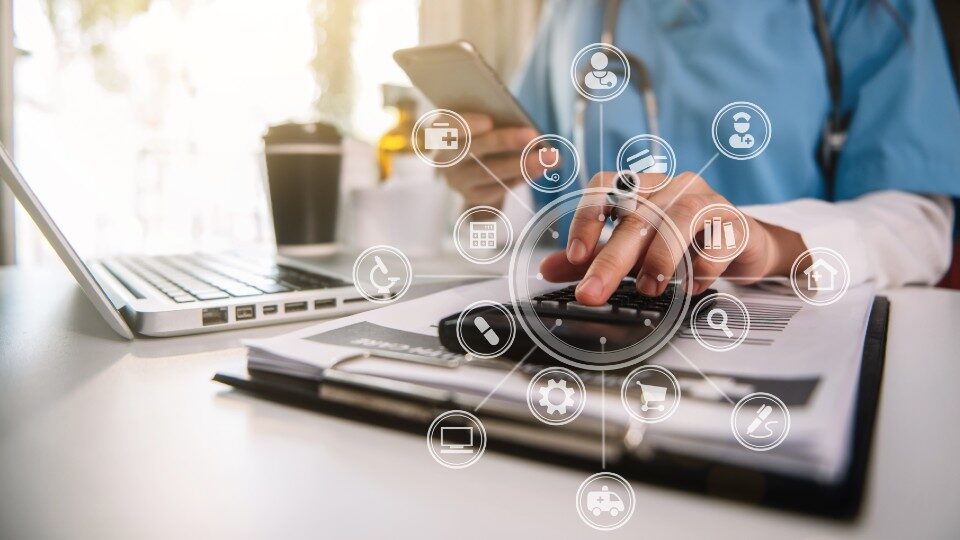
-
業種
病院・診療所・歯科
- 種別 レポート
赤字経営の病院が増加傾向にある昨今、コスト削減は重要な施策の1つです。中でも変動費に分類される材料費や委託費の適正化は「現場の負担を最小限に抑えながら行える経営改善策」として重要視されています。しかし、その価格交渉は容易ではなく、多くの病院が苦戦しているのが現状です。
そこで今回は、病院のコスト適正化の取り組みをテーマに、失敗事例と成功事例、成功に導くための考え方などをご紹介します。
病院経営の現状と課題
病院経営において変動費に分類される材料費や委託費は、患者数や医療提供に比例して増加するコストです。特に医薬品費や診療材料費は人件費に次ぐ費用となり、その割合は費用全体の2〜3割に及びます。これらの費用を適正化できれば、経営改善に有効なことは明らかです。
しかし昨今、とりわけ医薬品に関しては出荷制限が相次ぎ、薬価の低さからメーカーが開発に注力しづらい状況が続くなどして、十分な供給がなされていません。買い手からすると価格交渉がしにくく、病院経営は依然として逼迫状況が続いているのが現状です。このような状況下において、いかにして調達におけるコストを削減・適正化できるかが、病院が向き合うべき重要な課題の1つとなっています。
日本経営の「調達支援サービス」では、医薬品や診療材料の単価、外注検査や清掃、給食といった委託の契約金額を適正化するサービスを提供しています。価格分析から企業交渉まで、適正化プロセスのすべてをご支援しています。
[ 失敗事例 ]
~自己流の交渉に潜む盲点とは?~
病院が独自で価格交渉に取り組んだ結果、期待する効果を得られなかった事例を5つ紹介します。
【事例1】病院経営の窮状を根拠にして交渉するケース
失敗例としてよく見られるのが、病院経営の赤字を交渉材料として価格交渉を行うケースです。たとえコスト適正化の発端が収益性の悪化であっても、それを売り手に強調しすぎるのは悪手です。
経営不振と聞けば、売り手は「患者が減少しているのではないか」「この地域で生き残れないのではないか」というネガティブな印象をもち 、「売掛金の未回収リスクあり」と判断せざるを得ません。価格交渉どころか支払いサイトの短縮等を要求され、かえって取引条件が悪化することもあります。
【事例2】事務部門だけで交渉するケース
用度課や総務課など、物品調達管理を行う部署はさまざまですが、これら事務方だけで交渉をした場合、良い結果につながらないケースが多々あります。
企業の担当者は現場にもよく足を運んでいます。その際、現場のユーザー(医師や看護師)が「良い製品・会社だから使い続けたい」と製品や会社に強いニーズを伝えている場合があります。こうなると売り手は「値下げをせずとも取引を継続できる」と判断し、価格交渉に応じません。
【事例3】ベンチマークシステムだけに基づいて交渉するケース
ベンチマークシステムを活用し「他院よりも単価が高いから安くしてほしい 」と価格交渉に臨んでも、気持ち程度の値下げしか実現しなかったという失敗例です。
ベンチマークシステムの登場当初はかなりのインパクトがあり、要望どおりの値下げを実行する企業も多数見られました。しかし、ベンチマークシステムが普及した昨今、企業側も容易に交渉に応じません。地域性や採用経緯を軽視している点を突かれ、理論的に交渉を回避されたり、ベンチマーク以外に交渉材料がないことを見透かされ、はぐらかされてしまったりすることが多くなっています。
【事例4】共同購入でコスト削減を狙うケース
医薬品や診療材料の共同購入という仕組みもずいぶんと普及してきました。共同購入はコスト削減において有効であるものの、企画倒れになってしまうことがあります。
前提として、医薬品も診療材料も、病院によって価格にばらつきがあるものです。そのため、一部の病院ではかえって価格が高くなり、共同購入が成立しないケースがあります。あるいは入札の際、企業側が企画倒れを狙い、過去には談合によって高い価格を提示された ことがあったため、コスト削減を狙ったつもりが、かえって高額になってしまう場合もあるのです。
一方で、共同購入を上手に始動させた病院も存在しますが、 診療材料においては必ず新製品が登場し、相場自体が変動するものです。 定期的に共同購入の効果の検証や評価を行わなければ相場から乗り遅れ、数年後には高値で購入しているという病院も少なくありません。
【事例5】企業に提案を求めるだけのケース
「後発医薬品の提案など、安く調達できる方法を考えてほしい」と、企業側に提案を求めるケースがあります。これ自体は悪いことではないですが、提案を求めるだけでうまくいくケースは極めて少ないで しょう。
成功しない理由は主に2つあり、1つは企業が病院の機能や支払い制度を把握していないために、的外れな提案がなされてしまうこと。もう1つは、病院が企業の提案を適切に評価できないことが挙げられます。病院側もある程度自己開示をするとともに、提案をジャッジできるスキルを身に付ける必要があります。
[ 成功事例 ]
~企業行動を知る日本経営ならではの前向きな交渉支援~
【事例1】未来に向けたビジョンを企業と共有し、交渉を活性化
コスト適正化の活動目的を、病院経営の窮状打破ではなく、「地域住民のため」「担うべき機能(急性期や特定の治療等)を提供し続けるため」という未来志向型で語ることで、交渉を有利に進められた事例です。
企業は継続的に利益を得られ、売掛金を確実に回収できる病院との取引を望んでいます。したがって交渉時には、「長期にわたり安定的に取引ができる病院」であると示すことが重要です。現時点では赤字経営であっても、地域で生き残れる病院、あるいは中核的病院となるイメージを企業にもってもらえれば、交渉は前向きに進みます。
【事例2】病院が一枚岩となり交渉することで、不当な価格を回避
「コストに敏感な病院」というイメージを企業に定着させることで、相場より高い金額の見積もりを回避するとともに、持続的に交渉の優位性を築くことが可能です。
不当な価格を回避するには、企業と接点をもつ職員が一枚岩となって取り組む姿勢が不可欠です。
日本経営では交渉前の準備として、物品調達管理の担当者はもちろん、現場職員を含めた、職員のコスト意識の醸成を図ります。
現場職員の中でも、薬剤師や手術室看護師は価格交渉に消極的な傾向があるため、必要に応じて説明会を実施します。これにより、病院全体のコスト意識も高まります。
【事例3】中長期のパートナーシップを前提に交渉し、価値ある情報を獲得
通常、企業は社内の好事例や新製品情報など、病院にとって価値があり鮮度のいい情報をもっています。しかし、病院への情報提供を面倒に感じている企業担当者がいるのも事実です。
企業担当者から価値のある情報を引き出すには、病院が取引企業を信用していることをしっかりと示す必要があります。そのうえで、中長期のパートナーシップを前提に交渉し、コスト適正化を実現している病院も存在します。
日本経営では、パートナーシップを築く企業の選定、価格交渉に応じてくれた場合の相手にとってのメリットの検証など、交渉をスムーズに進めるための戦略策定をサポート。「〇〇病院さんに育ててもらった」と企業担当者に言ってもらえるような関係構築を支援します。
【事例4】入念な根回しで共同購入を成立させ、コスト削減を実現
成功すればコスト削減に大きな成果を生む共同購入。しかし、取引企業も人材不足や物価高に悩んでいるため、まとまった売上が立つような商機であっても、必ずしも意欲的に参加するとは限りません。そこで重要なのが、共同購入への参画を動機付ける根回しです。
日本経営の支援では、まず取引企業の支店長クラス以上の役職者と接点を作り、「共同購入によって優位に立つサプライヤーとなることで得られる経済的メリット」と「地域にある他院への波及効果」を具体的に提示。双方にメリットのある状態で共同購入取引を締結しました。共同購入事案で当社が支援した50病院のうち、8割の病院でコスト削減が実現しています。
コスト適正化を成功に導くポイント
コスト適正化を実現するには、ビジネスと企業構造の理解が不可欠です。最後に、コスト適正化に向けて取り組む際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
■ ポイント1:BtoBビジネスの基本を理解しよう
まずは、BtoBのビジネスがどのようなものなのか、あらためて基本に立ち返ることが重要です。病院と企業は法人間取引(BtoB)となり、原則として製品・サービスの売値は公開されません。加えて、法人間取引の価格は流動的なため、企業は当然、高く売って利益を得る行動に出ます 。
つまり、適切な交渉をしなければ、高値で買う構造となっているのが法人間取引の特徴です。逆に言えば、病院側の努力や工夫次第で安くなる可能性は大いにあるということです。
■ ポイント2:売り手のことを知ろう
病院経営の厳しさは企業も理解しているところですが、病院を取り巻く企業も同様に、経営の先行きに不安を抱いているのが現状です。各社生き残りをかけ、戦略や計画に沿って価格を決定し、販売活動を行っています。
こうした状況において、病院・企業の双方にメリットのある取り組みの投げかけは、たとえ成果の確実性が見えなくても好転のチャンスと受け止められ、喜んで協力してくるケースもあります。企業行動を理解すると同時に、企業が求めるものを病院側から提示することも大切です。
\いまの運用を変えずに、医薬品コストを削減、単価交渉も不要に!/
日本経営の「医薬品コスト削減コンサルティング」
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。





