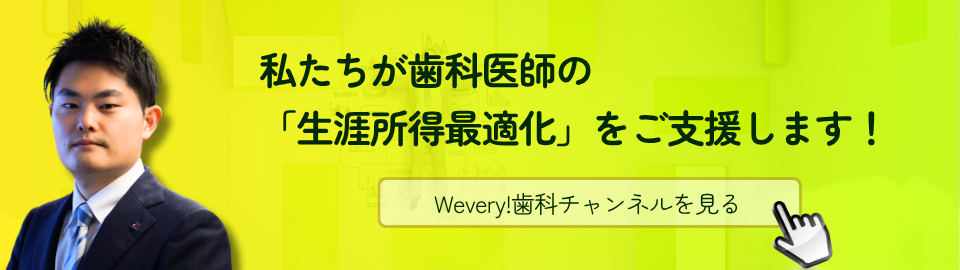歯科医院にお金が残る収益改善 自費率 アップを支える4つの柱

-
業種
病院・診療所・歯科
- 種別 トピックス
近年、歯科医院経営は転換期を迎えています。保険診療の報酬が伸び悩む中、材料費や人件費の高騰は経営を圧迫し、これまでの保険診療中心の経営モデルでは限界が見え始めています。このような厳しい状況下で、持続可能な経営を実現し、地域に選ばれる歯科医院となるためには、自費診療による増収が重要であり、戦略的な導入と仕組み化が不可欠です。
本記事では、自費診療を成功させるための戦略と実践的なアクションプランをご紹介します。特に、自費診療を増収させるための施策として、患者への情報提供の強化や、質の高い治療を支える体制整備など、利益率向上と収益改善を両立させる施策について詳しく解説します。
歯科業界の現状
現代の日本は超高齢化社会に突入しており、「健康な歯を長く保ちたい」「高齢になっても自分の歯で食べたい」といった健康志向が高まっています。加えて、ホワイトニングや小児矯正治療など、見た目の美しさを求める審美ニーズも非常に伸びています。
しかし、保険診療の制度や材料は長年ほとんど変わっておらず、診療報酬の伸び悩みに加え物価高騰(材料費・人件費)も重なり、保険中心の医療経営には 限界が見え始めています。こうした状況から、自費診療への取り組みはもはや「プラスアルファ」ではなく、経営を支える「柱」として真剣に考えるべき局面に来ていると言えます。
一方で、多くの歯科医院では、自費診療の重要性を理解しつつも、自費診療が「仕組み」として定着していないのが現状です。主な課題は以下の通りです。
- 患者さんへの説明が曖昧で不信感を与えてしまうケースがある
- 自費診療の価格設定は感覚値で決まっている
- 自院の自費メニューが患者に認知されていない
令和7年2月末時点で、全国の歯科医院の数は約6万6000件であり、これは全国のコンビニの約1.2倍に相当します。地域内の競争は激化しており、加えて、子どもの虫歯は過去数十年で大幅に減少しました。もはや「自然に患者が集まる時代」は終わったと言えます。材料費や人件費が上昇し続ける一方で、保険診療の報酬は数年間かわっておらず、保険診療だけで利益を出すことは非常に難しい状況です。
このような背景から、保険診療ではカバーしきれない部分を補い、医院の収益基盤を安定させるために、自費診療の導入・拡充が不可欠となっています。
これからの歯科医院のあるべき姿
厳しい環境下で患者さんに選ばれ続ける歯科医院となるためには、以下の要素がカギとなります。
- 患者さんに「信頼」され、「選ばれる」医院であること
選ばれる理由は、「治療そのもの」から「誰から受けるか」にシフトしています。 - 納得と満足を伴う「自費診療サービス」を提供すること
単に高額な治療を勧めるのではなく、「自分にとって必要だ」と患者さんが腑に落ち、「受けてよかった」と実感できることが重要です。これが医院の信頼や口コミ、ブランディングに直結します。 - 「再現性」を高く提供できる「体制づくり」
一部のスタッフに依存する属人的な営業トークではなく、誰が対応しても一定の品質で自費診療の提案、カウンセリング、成約まで進められる仕組み化・標準化されたチームづくりが求められます。
これからの時代は、ただ良い医療を提供するだけでは不十分であり「選ばれ、満足され、経営が成り立つ」歯科医院であることが求められます。そのためには、自費診療を組織の仕組みとして組み込むことが重要です。
これからの自費率アップ推進施策:4つの柱
自費率アップの柱1: 価格ではなく、価値を伝えるカウンセリングと導線の構築
自費診療を提案しても「高いから」と断られる主な理由は、患者さんがその価値を十分に理解していないことにあります。患者さんが自費治療を断る理由としては、「価格が高いと感じる」「必要性を感じない」「違いがよくわからないなどがありますが、いずれも情報不足や価値が伝わっていないために生じる拒否反応です。
重要なのは「どう説明し、どう伝えるか」です。一方的にメリットを並べるのではなく、患者さんが納得し、興味を持ち、自分で選べる形に導くことが求められます。例えば、「セラミックの方がいいですよ」と伝えるのではなく、「銀歯とセラミックの違いをご存知ですか?」と問いかけることで、患者さんが「自分で選んだ」と感じられます。
また、医院全体で一貫した導線を設計することも大切です。受付での声掛け、チェアサイドでの会話、カウンセリングルームでの提案、説明資料の使い方まで、全てが統一されていれば、患者さんは「勧められたから」ではなく「納得して自分で選んだ」と感じ、自費診療を受け入れます。
自費率アップの柱2: 材料費・人件費・稼働率を踏まえた利益が出る価格設定
自費診療の売上が多いからといって、必ずしも利益が多いとは限りません。重要なのは、「利益をしっかり上げているかどうか」です。
例えば、以下の2つの医院を比較してみましょう
| 医院A | 医院B | |
| 自費売上 | 500万円 | 700万円 |
| 材料費率 | 30% | 40% |
| 材料費 | 150万円 | 280万円 |
| (材料費差引)利益 | 350万円 | 420万円 |
次に人件費を加味します。
月に30件の自費診療があり、スタッフの時給を2,000円と仮定した場合
最終的な利益と利益率は以下のようになります。
| 医院A | 医院B | |
| 利益 | 344万円 | 408万円 |
| 利益率 | 68.8% | 58.3% |
このように、売上額だけを見ると医院Bの方が優れているように見えますが、利益率で 比較すると医院Aの方が効率的に利益を上げていることがわかります。チェア稼働率や管理業務などの間接人件費を含めると、非効率な体制はさらに利益率を低下させます。
売上や自費率といった数字はわかりやすい指標ですが、真に注目すべきは材料費・人件費・稼働効率といったコストを踏まえた「利益率」です。特に自費率は、保険診療の売上が減少すると自動的に上がる性質があり、数字の錯覚に注意が必要です。
また、スタッフの時間は重要なコストであることを忘れてはなりません。マニュアルが整っていても、体制や運営が不十分であれば、同じ説明を繰り返したり、業務が属人化し対応にばらつきが生じたりするといった非効率な業務フローが発生し、人件費が増大してしまいます。
自費診療に取り組む際には、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
- 診療ごとの原価を、しっかりと数字で把握する
- 材料費や人件費を管理し、利益が出る価格を設定する
- 無駄や属人化を見直し、効率的で生産性の高い仕組みや体制をつくる
これらの取り組みが、自由診療を推進し、医院経営の安定と成長につながります。
自費率アップの柱3: ウェブマーケティングによる「選ばれる医院」づくり
患者さんは来院前にウェブ上で情報収集を行い、安心して選べる医院を探す傾向が強まっています。特に審美分野に対する興味・関心は高まっています。
ウェブサイト等には、自費診療のメニューを明確に記載し、治療の説明、期間、料金の透明性を示すことが、患者さんの安心感につながり、選ばれるためには欠かせません。
また、SNS投稿やGoogleマップの活用(口コミ)など、初期コストや運用負担を抑えつつ、継続的に情報発信を行う工夫も重要です。
ウェブツールは存在するだけでは意味がありません。医院の理念やスタッフの想いを伝え、治療の特徴や流れを丁寧にわかりやすく示すことで、信頼と安心感を醸成する「ブランディング」こそが、選ばれる医院になるための重要なカギとなります。 見た人が自ら選びたくなるような情報発信が重要です。
自費率アップの柱4: チームで取り組むためのスタッフ教育と共通認識づくり
自費診療を医院に根付かせるためには、院長だけではなく、 スタッフ全員が心を一つにして取り組むチーム体制が不可欠です。しかし、多くの医院では院長の理念や診療方針がスタッフに十分に浸透しておらず、「保険診療より高価な自費診療には抵抗がある」「自分にはうまく説明できない」といった心理的な壁(メンタルブロック)を抱えていることも少なくありません。
自費診療は決して「高い治療を売る」ことではありません。むしろ、患者さん一人ひとりの「未来の健康」を考えた「選択肢の提示」です。スタッフがその価値を理解し、自信を持って患者さんに伝えられることが重要です。
医院全体で共通の価値観を持ち、患者さんに伝える体制を整えるためには、院内ミーティングや教育の場が欠かせません。ただの報告や形式的な集まりで終わらせず、具体的な課題や成功事例を共有し、スタッフの不安や疑問を解消しながら理念を共有する「意味のある」時間に変えていく必要があります。また、目標となる数値を掲げ、定期的に実績を共有することも大切です。
歯科の自費診療を根付かせるために今できること
これまでの4つの柱に共通しているのは、「感覚に頼らず、数字と仕組みで考えること」「一人ではなくチームで取り組むこと」、そして「継続的に改善していくこと」の重要性です。
患者さんとの接点である医院の「外側」(カウンセリング、ウェブマーケティング)と、組織やチームの土台となる医院の「内側」(価格設定、スタッフ教育)の両面がしっかり整っていることが、自費診療を自然かつ持続的に提供していくための基盤となります.
医院経営の安定と成長のためには、財務戦略の立案や経営データの適切な管理が不可欠です。収支状況を定期的に分析し、利益率の高いメニューの見極めや投資の優先順位を明確にすることで、限られたリソースを最大限に有効活用し、持続可能な成長を支える土台が築かれます。
すべてを一度に変える必要はありません。大切なのは「できることから始めること」です。ぜひ、以下の具体的なアクションから、まずは実行可能な一つを選び、段階的に取り組んでみてください:
- 院内POPやパンフレットの配置場所を確認・改善する
- 自費メニューの価格設定を見直すきっかけをつくる
- ホームページに記載している自費診療の説明が、患者目線でわかりやすい内容になっているかをチェックする
- スタッフ全員で「自費診療に対する想い」を話し合うミーティングを一度催してみる
これらの小さな改善の積み重ねが着実な成果となり、地域に根付いた「選ばれる医院」へとつながっていきます。
歯科専門のコンサルタント・専門家が、未来に向けて伴走支援します
Wevery!歯科チャンネルにも登場中!
本稿は、歯科経営で判断を迫られるテーマに対して、専門家が前提条件なしに直観的な回答を述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。