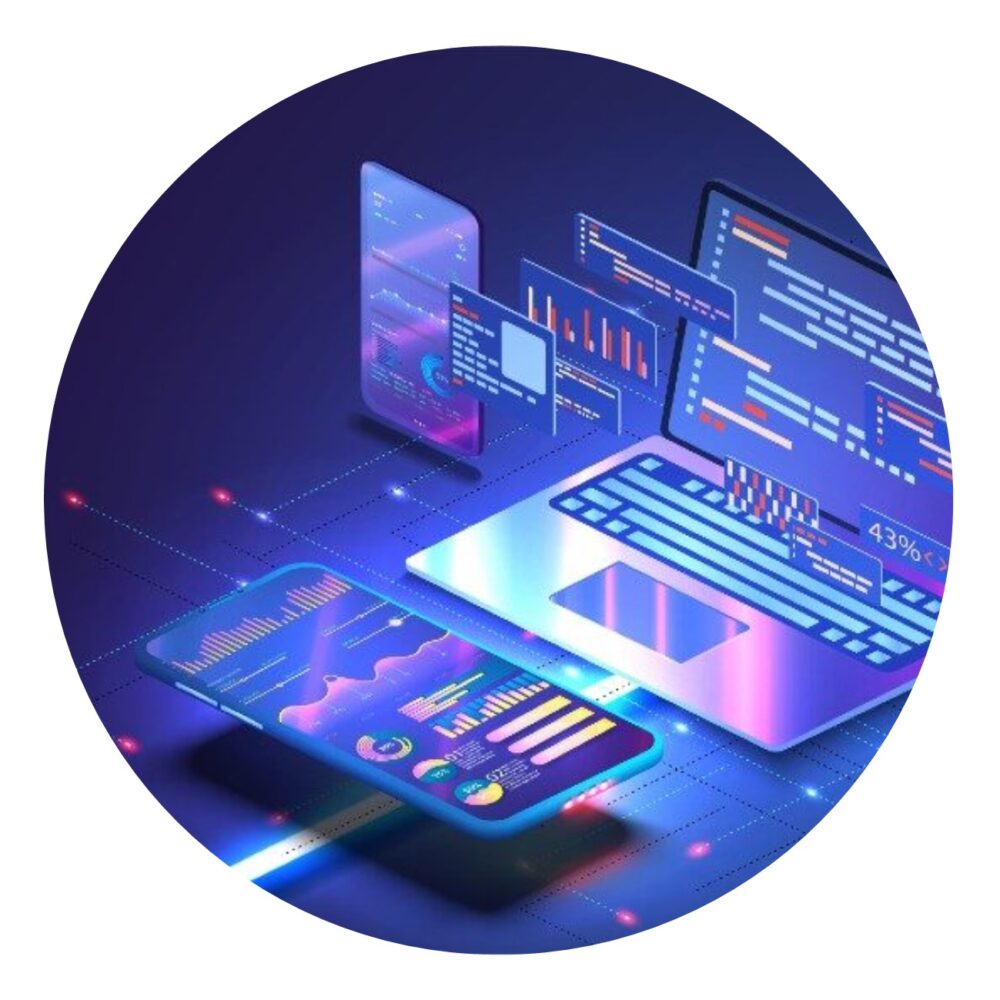LIFE活用時代 介護施設の稼働率を上げるチームケアの実践
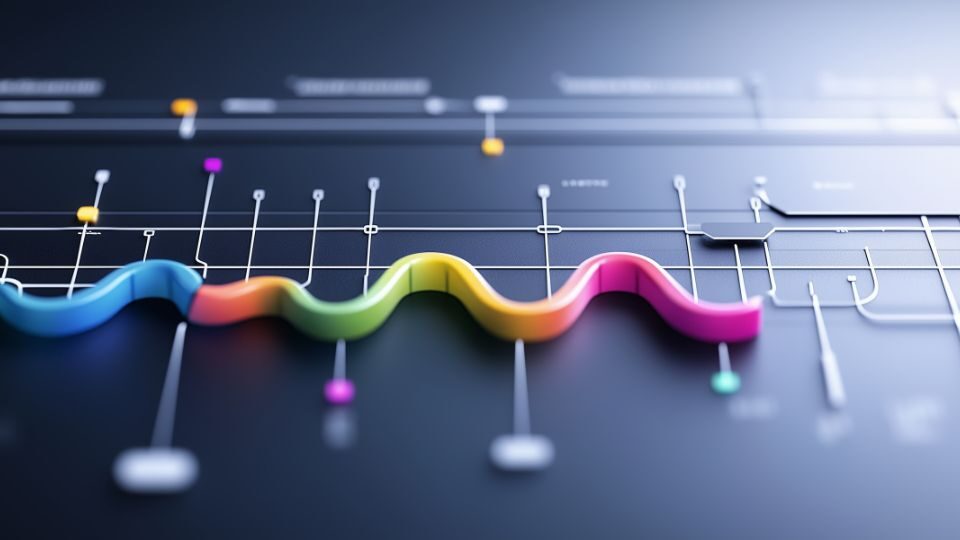
-
業種
介護福祉施設
- 種別 レポート
重度化や医療依存度の高い利用者が増えている一方、人材不足が深刻化しており、経営面と現場運営が同時に厳しい状況へ追い込まれるケースが増えています。そこへさらに、令和6年度介護報酬改定をはじめとした“成果報酬型”の強化や、LIFE(科学的介護情報システム)の本格運用が進むことで、利用者の状態改善や重度化防止の成果がこれまで以上に求められる流れとなっており、従来の“経験則”によるケアではなく、根拠に基づく判断と多職種連携を組み合わせるクオリティ・マネジメントが、今後の介護施設運営の鍵を握ると考えられています。
なぜ今、LIFE時代のクオリティ・マネジメントが必要なのか
大きな理由は二つあります。一つ目は、施設の稼働率を安定して維持することは、そもそも簡単なことではないということです。入院や状態悪化により空床期間が生じると、ベッド数に合わせて配置している職員の人件費や光熱費などの費用がかさみ、、経営を圧迫します。実際に、要介護度の高い利用者が頻繁に入院を繰り返すと、年間にして数百万円単位の収益損失につながることも珍しくありません。逆に言えば、クオリティ・マネジメントを取り入れて利用者の状態を安定させ、入院を減らすことができれば、稼働率が上がり、経営が安定化し、加算算定のための要件を満たしやすくなるのです。
もう一つの理由は、報酬改定の評価指標が、「構造・過程・実施量の評価」から、目標の達成度や数値目標に対する結果を評価する「アウトカム評価」へとシフトしてきていることです。“自立支援”“重度化防止”を色濃く打ち出し、成果を評価する傾向を強めているのです。代表例として、ADL維持等加算や排せつ支援加算などが挙げられますが、今後はLIFEへのデータ提出とフィードバック結果を活かして利用者の機能維持・改善を図る取り組みが、より高く評価される見通しであり、加算を取りやすい体制づくりを怠ると、同規模の他施設と比べて収支面で後れを取ることになりかねません。
こうした背景から、「ベテランスタッフの経験と勘」に頼りがちだったケアを、より科学的アプローチに近づけるための方法としてクオリティ・マネジメントが注目を集めています。具体的には、多職種が定期的に情報を共有し、利用者一人ひとりの睡眠・食事・水分量・排せつパターンなどを数値データとして把握し、それを根拠にして仮説検証を繰り返していく体制を整えことが大きなポイントです。
LIFEを活かすクオリティ・マネジメントの実践ステップ
多角的なアセスメントとチーム連携が要
1.生活全体の記録とデータ化
クオリティ・マネジメントを導入する際、はじめのステップとして重要なのは、食事・水分量・排せつ・睡眠など基礎介護にまつわる情報を丁寧に記録し、ある程度の期間で振り返る仕組みを作ることです。
1日に何ccの水分を摂れているのか
起床から就寝までどのような活動を行ったか
排便や排尿はどのようなタイミングで起きているか
利用者が普段の生活で当たり前に行う動作を数値化して追うことが欠かせません。こうしたデータは、紙ベースの総合記録シートやICTシステムでも構いませんが、スタッフ間で共有できる形が理想です。
この段階で、毎日の記録と1週間〜1か月単位でのダブルチェックを組み合わせると、些細な体調変化を見逃しにくくなります。たとえば、5日間連続して平均水分摂取量が基準値を下回っている利用者がいる場合、今までは「経験則」で解釈していた変調をデータを根拠として把握できるようになるわけです。この小さな発見の積み重ねこそが、入院や状態悪化を未然に防ぐうえで重要です。
2.多職種カンファレンスと仮説立案
集めたデータを多職種で検討して、なぜその利用者に特定の症状が出ているのか仮説を設定する段階です。看護職、介護職、リハビリ職、栄養士、ケアマネージャーなどが同じテーブルで話し合う機会を定期的に設けることで、身体機能・認知機能・栄養状態・薬剤副作用など複数の要素を用いた総合的な判断が可能となります。とくに夜間の不穏や昼夜逆転傾向、便秘や誤嚥性肺炎のリスクが高い高齢者などは、このような多角的なアプローチが有効となるでしょう。
夜間に転倒を繰り返していた方の場合、単純に認知症状が原因と考えるのが普通だと思います。しかし、記録の中の情報から、日中の水分摂取が極端に少ないために夜間に脱水傾向となり、せん妄のような状態を起こしているのではないかという、これまでになかった仮説が浮上することがあります。そのような仮説を得たら、それを解消するケアプランを具体化し、チーム全員で統一の取り組みを行うのです。こうした連携が成立すれば、利用者の安定だけでなく、リーダーや管理職がスタッフをまとめやすい環境づくりにもつながります。
3.結果検証とケアプラン修正
実際に取り組んだケアの結果を再びデータで検証し、うまくいかなければ新たな仮説を設定してリトライする、このサイクルを回すことがクオリティ・マネジメントのポイントです。
たとえば、水分摂取を1日平均で200cc増やすケアを行った結果、夜間の興奮や昼間の傾眠状態が改善するケースもあれば、むしろ別の要因が表面化してくる場合もあります。重要なことは「失敗や変化の見落としを、データを通じて客観的に捉え、次のアクションに結びつける」ことです。いずれ“経験則”によるケアとは比べものにならないほど、“チームとしてケアを実践する力”が育つようになり、入院率の低下や利用者満足度の向上を後押しします。
稼働率と加算を左右するLIFEの本格運用
成果報酬型の“次の時代”へ備える
前述のとおり、近年の報酬改定では、ADL維持等加算や褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算など、成果を重視する傾向が明らかです。その背景には、介護施設がLIFEにデータを提出し、国や自治体が蓄積されたビッグデータを用いて科学的根拠に基づくケアを推進したいという狙いがあります。実際に、LIFEのフィードバックをどれだけ活用してケアの質を高めているかが、加算取得や将来的な減算回避の大きなポイントになると言われています。
まだ算定率が低い加算や、取得したくても手間がかかるという声が多い加算については、見直しのない一定の“リード期間”が続くというのが業界の一般的な見方です。しかし、一定以上の取得率に達した場合、加算が本体報酬へ組み込まれたり、未実施の場合に減算されたりするといった見直しが進められる可能性は十分にあります。こうした制度変更への備えとして、クオリティ・マネジメントを早めに導入し、データ収集と活用のスキルを高めておくことが、今後の安定経営の鍵になるでしょう。
関連するサービス
介護と言えば、日本経営!
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。