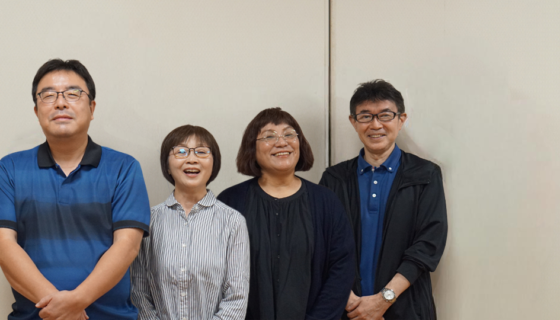【お客様インタビュー】コンサル活用のポイントは、客観的視点の「地図」

担当コンサルタントが聞く
社会福祉法人でのコンサル活用のポイント
- 介護福祉施設
- 収益向上・経営改善
- 組織・人事マネジメント
- 101人~300人
コンサル活用のポイントは、客観的視点の「地図」
どの道を行くか迷った時にコンサルタントが冷静に現在地を示してくれた

事業者名:社会福祉法人育徳園
所在地(都道府県):大阪府
事業内容:高齢福祉事業、保育・学童事業、障がい福祉事業 等
従業員数:約200名
URL:https://ikutokuen.or.jp/
話し手:事務局長 T様、経営企画管理本部 事業本部長 H様、高齢事業 本部長 Y様
●支援内容(コンサルのプロセス)
2022年6月から2024年10月までの約3年間、「課題ヒアリングと分析」~「グランドデザインの作成・共有」~「賃金と等級の設計」~「人事考課制度の設計・運用・研修」に取り組む。
● 導入効果
・縦割り組織を横串でつなげる事で稼働率の向上、新規事業開始による事業規模拡大が収支改善に貢献
・経営幹部やリーダー層の世代交代で組織を活性化し、職員の意識改革も定着しつつある
コンサル導入の経緯と支援内容
構造改革の地図と、自分たちが成長するための武器を手に入れた
数あるコンサル会社の中から日本経営を選んでくださったのはなぜですか?
T:大阪府下で介護事業所の運営をされている同業の方からの評判が決め手です。そこは一般企業のような経営をされている法人さんなので、共感する部分がたくさんあり、お聞きしたコンサル料金もリーズナブルだったので、日本経営さん一択で進めました。
ただ、最初に日本経営さんに問い合わせをした際、電話を受けられた方(その後、当園の人事改革の担当者となる方)がやたらと愛想がいいので、信用して大丈夫だろうか?と少し不安になりましたが(笑)
Tさんは前職でコンサルを使った経験をお持ちでしたが、日本の福祉業界ではまだまだ一般的ではないと思います。YさんやHさんから見て、われわれ日本経営はどう見えましたか?
Y:私はずっと育徳園の特養に所属し、介護職、相談員を経て、当時は副施設長を務めていました。人を一番大事にしなければならない業界なのに、そこへテコ入れをすることへの躊躇もあって…。なので、私は日本経営さんからしっかり学ばせてもらおうという気持ちでいました。
H:当時私は単独デイサービス(高齢事業)の施設長でしたが、本部のサポートも並行して行っていました。自分なりに10ヵ年計画を立てるなどして施設の将来を考えていたので、正直、日本経営の皆さんとは疑問符の多い状態でお会いしています。自分たちが勉強してノウハウを得たほうが効率的なのでは?とも思っていました。
日本経営のコンサルで印象的だったことを教えてくださいませんか?
H:私が印象的だったのは、最初のプロセスである分析とグランドデザインです。そこには、自分たちが今どの地点にいて、目標までどのくらい離れていて、どのルートが選択可能なのかが明確に示されていました。まさに構造改革の地図です。これまで持っていたのが住んでいるエリアの地図だとしたら、大阪市全体の地図を手にいれたような感覚でした。ただし、あくまで地図なので、どの道を選ぶかは自分たち次第です。


また、未来のリスクに対するアプローチ方法が、今まで考えたことのない方法で記されていました。
なるほど、コンサルタントというのは、自分たちが成長するための武器を与えてくれる存在なのだと、日本経営さんとお話しして初めて知ることができました。
Y:私が不安だったのは、賃金と等級制度についての面談です。面談では職員に対し、減給や降格の可能性も示さなければなりません。これから皆でモチベーションを上げて結果を出していかなければならないのに、大丈夫なのだろうかと。
その不安を察してか、日本経営さんが事前に職員に対し、経営状況と目指すべき方向についての説明会を行ってくれました。
その後、当時の施設長の力を借り共に高齢事業の全職員130名と面談しましたが、「なんとかして園を守らなければならない」と各々が考える面談となり、逆に皆から力をもらって。私が揺らいでいてはいけないと、覚悟が固まりました。
コンサル活用の成果
福祉の現場で学んできたスキルとは違う、経営者的な意識が芽生えた
取り組みを開始しておよそ1年でより一層の経営発展をされていますが、具体的にどのような成果を得ましたか?
T:特養で稼働率95%前後を維持できたのも大きいですし、デイサービスの稼働率が大きく伸びました。これは、経営数値の見える化・共有を図り、職員さんが数字を意識して取り組んだ結果です。
2024年4月から地域包括支援センターの運営、理念の似ているNPOさんと協業し、新たに就労継続支援B型の運営もスタートしています。
Y:頑張りは職員の収入にも反映され、2024年度は給与4ヶ月分以上の賞与を支給することができました。また、これまで老朽化対策もできずにいましたが、今後10年間の設備改装計画を策定し、2025年から浴室改修に着工。職員からも喜びの声が上がっています。

H:定性的な効果でいうと、課題の捉え方であるとか、経営の考え方であるとか、私たちが福祉の現場で学んできたスキルとは違うものを、日本経営さんと歩んできた3年間で学ぶことができました。役職者だけでなく、職員にもそういうスキルが身につき、経営者的な意識が芽生えているところが、すごいと思うんです。
少しずつですが確実に、一人ひとりが考えて動ける組織に成長してきていると実感しています。
コンサル活用の成果ポイント
不安になったら現在地を冷静に示してくれるのがコンサルタント、どんどん迷いを伝え、たくさん提案してもらう
コンサルの導入を検討されている事業所様に向けて、コンサルを使う価値や活用時のポイントを教えてください。
H:新しい課題に取り組むときは、現在地と目的地が明確に示された「地図」が欠かせません。そしてその地図の作成には、外部の人の客観的な視点が不可欠です。なぜなら、同じ組織にいる人間同士だと、頑張っていることを否定できず、方向を見誤ってしまうことがあるからです。
目的地に進むのはあくまで自分たちですが、時々、この方向で合っているのか不安になることがあります。そんなとき、現在地を冷静に正しく示してくれるのがコンサルタントだと思います。その価値は、思った以上に大きなものです。

Y:私もHと同じ考えです。これは自分の経験でもありますが、解決の手立てが分からぬまま取り組んでも、時間と労力を消費するだけで、誰も幸せにならないんですよね。
もし、解決の方法に迷うのであれば、その迷いをコンサルタントに伝え、たくさん提案してもらえばいいと思います。あとは覚悟を決めて選択し、行動するのみです!
T:法人の構造改革は、容易なことではありません。仮にコンサルタントを導入してうまくいかなかったとしても、「コンサルのせいではなく自分たちに責任がある」くらいの覚悟を持って取り組むことが大事なのかなと。そうすることで内部のコンサルに対する抵抗感がなくなり、一人ひとりが自分事として課題に取り組み、想像以上のパフォーマンスを発揮することがあります。今回の取り組みの中で、私はその光景を目の当たりにしました。
担当コンサルタント:多くの職員の方にヒアリングのお時間をいただき、その発言の節々から、まさにゆりかごから墓場までを支える育徳園様のブランドを感じ、そのブランドをより一層発展させられるよう、コンサルティングを行いました。支援中にはこれまでの育徳園を支えて来られた方々と、これからの育徳園を支えていかれる方々、両方にご協力いただき、ブランドを保ちつつ新しいステージに向かうためのお力になれたのではないかと感じています。
日本経営では700件近くの介護施設支援の実績がございます。介護施設の経営にお悩みの場合は、私たちコンサル活用の選択肢もぜひ、ご検討ください。